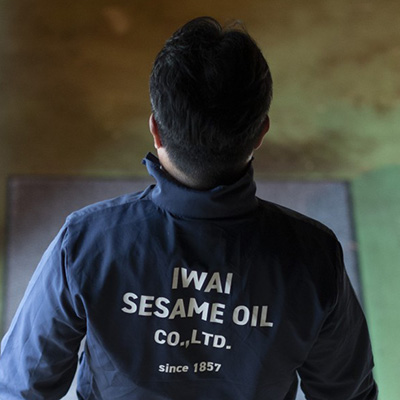会津若松に酒蔵を構える宮泉銘醸と日本香堂の想いが結実し、新たな銘酒が生まれた。
その名は「暁霞(あきがすみ)」。
日本香堂グループ450年を記念したこの酒は、夜明けに咲く花の朝露のような、これまでにない香りもつ。
誕生までの経緯を知るべく、静謐で美しいその酒蔵を訪ねた。
銘酒「暁霞」はなぜ生まれたのか
「香」をつくる会社である日本香堂が、なぜ「酒」をつくったのか。フランスで定期的に香道を催し、ESTEBAN社も子会社としており、様々な香りづくりも進めている。
「フランスで長年仕事をしていて、よい香りや美味しさの感覚が、日本人とフランス人では異なるでないかと思いました。フランス人は、分析的でより複雑な要素があるものを良い香りとする。多分美味しさもそうでしょう。日本人はシンプルに全体をとらえて良い香りとする。大きな違いがあるのではないか。今年『日本の香』という書籍を出版したのですが、インタビューを重ねる中で、そのような分析的な思考こそが、トップからラストへと変化する香水文化を育んできた事に気づかされました。そこで、複雑な香りの、お香と日本酒を作ったら、日本の方々はどう感じるのかと興味が湧いてきました。」(小仲社長)
そこで、複雑な要素を持ったお酒造りについて、長年ご縁があり、尊敬する宮泉銘醸の宮森義弘社長に相談した。始まりは日本香堂ホールディングスの小仲正克社長と、グループの一つである銀座らん月の唎酒師、坂本幸志が宮泉銘醸の宮森義弘社長との長年の交友があったことに端を発する。
「らん月と長年のご縁もあり、初対面で宮森さんのものづくりに対する情熱とストイックさには大いに感銘を受けました。我々はものづくりにおいて、そこまでのことができていないんじゃないか。そういう問題意識をもつようになり、日本酒に学び、香り作りに生かせたらと思いました。ただ、当時はお酒造りをお願いする事になるとは思っていませんでした。らん月や酒の穴は、蔵元とお客様をつなぐ交差点と考えていますので」(小仲社長)
それはものづくりの原点に立ちかえるということだったのだろう。
そのなかで、小仲社長が香と日本酒づくりにある種の共通点を見出したことも大きかった。
「香りをつくる過程で、トップノート、ミドルノード、ラストノートを構成していきますが、日本酒も立ち香、含み香、戻り香というのがある。最初の香り、それから口に含んだときの香り、鼻に抜けていく香り。それは並行複発酵という世界に類を見ない複雑な発酵過程によって生まれていくのですが、宮森社長と専務にお話を伺うと、表層的なもの以上に、問題意識や考え方、高い処方設計力や技術力、経験、そして人の熱い思いが求められることを知りました。そしてそのプロセスと人に魅惑されました。お香と共にお酒も造ってみてはと思い、何度も通って無理難題をお願いしました」(小仲)
実際に酒造りを担当したのは、宮泉銘醸の宮森大和専務。
「実はこういったケースは、ほぼお断りしています。けれども、小仲社長とらん月の坂本さんとで熱意をもって何度も足を運んでいただき、これはやるしかないと思いました。構想からは2年近くかかっているでしょうか」。(宮森専務)

霞が、雲が、いろんな複雑な色合いを醸す。そんなお香と酒を
酒名の「暁霞」は、小仲社長から上がった。
「佐賀県の嬉野に行ったとき、ちょうど春だったので、朝靄が立つんですね。霞(かすみ)は和歌でもよく使われる美しい情景です。暁(あかつき)、つまり明け方、ちょうど太陽が昇るときに、その霞がいろんな複雑な色合いを拾うんです。その複雑な美しさは、お酒にもお香にも通じるなと思いました。それで同じ名前の、お香とお酒をつくろうと思ったのです」(小仲社長)
それを聞いた宮泉銘醸の宮森専務とスタッフは、その酒の設計に粉骨砕身することになりました。
「複雑で、トップとラストのところをちゃんと感じるような味わいにしなくてはと思いました。層になるようにつくるには、まず米を変えてみたらどうかと。熱のこもった話し合いでした。20種類近くの全国、福島の酒を並べて、どの香りが良いのかというのを、小仲社長、坂本さんと探っていきました」(宮森専務)
宮森専務の隣では、右腕の市田元樹製造部長が飲みながらも細かくメモをとっていた。
香りのポイントとなるのは、酵母だという。
「どの酵母をどの割合で、どういう温度管理で香りを引き出すかというのが大変で。でもやっぱり、経験したことのない酒を造りたいので。酒だけが美味いんじゃなくて、銀座らん月の一流の料理にも合わないといけないわけですから。ただ、僕の一番の想いは、小仲社長と坂本さんが『すごくいい』といってくれる酒をつくろうということでした」(宮森専務)
そこでよかったのは、小仲社長と坂本さんの「美味い」が同じだったことだった。
「ふたりの嗜好がバラバラだったら迷惑だったと思います。(笑)坂本さんは唎酒師という立場上、普段は自分の好みに対しては抑えていると思うんですが、そこは本当に良かったと思います」(小仲社長)
ふたりの「美味い」は、もちろん香りと味わいが両立するものだった。
「トップ、ミドル、ラストまで香りが立ち、味わいもきちんと伝わり、かつ料理との相性も良いこと。香りはありすぎてもいけないし、無さすぎてもいけない。味も強すぎてもいけないし、平坦すぎてもいけない。しかし最後まで旨みを感じるようにとお願いしました」(坂本)。
理想が完璧な形になったような酒。それはまさに宮森専務たちも「つくったことのない酒」だったに違いない。


三つの酵母をブレンド。立ち香も含み香も味わいもある酒に
お香作りには試作もあるが、日本酒は一発勝負。
「醸造工程だけでも1ヶ月半はかかりますし、再現性が難しいので、今回の酒は一発勝負なんです。酵母の機嫌ですべてが変わりますから。どうやっておふたりが好きな香りを引き出すか。うちの酒は含み香に酢酸イソアミル系のF7-01酵母を使うことが多いんですが、今回は立ち香が強めのカプロン酸エチル系のきょうかい1801号という酵母も使い、香りを立たせるため福島県の煌酵母も合わせました。米は喉越しのいい五百万石と、ふくよかでパンチのある福乃香を使いました。この二つの米と三つの酵母の処方設計のバランスが一番気を使いましたね。そしてそれを実際につくるということも。つまり、5つそれぞれに対するアプローチが全然違うので。かなりシビアに管理しました。ここまで複雑に、香りをメイン軸として酒造り設計を考えるということは日本酒業界で初めてだと思います」(宮森専務)
三つもの酵母を並行複発酵させる。至難の技術は宮泉銘醸ならでは技術だった。
出来上がった酒を味わった小仲社長と坂本の目には涙さえあったという。
「生酒も火入れした酒も素晴らしかった。ひと口の酒に、まず立つ香りがあり、味わいと共に香りがあり、喉元を過ぎてからも、ものすごい余韻がある。変化していく。まさにひと口の酒に香りの旅ができるような。我どものステイトメントの『香りと旅する』ように、味わいはそれぞれの方々に委ね、香りとともに時空を旅して頂けたらと」(小仲社長)
出来上がったボトルは透き通ってほのかに金色がかっている。暁の日の光がここに詰まっている。
ひと口、味わわせていただいた。
最初に夜明けに開いたばかりの花のような香りが鼻腔を豊かに満たし、口に入れると甘さからやさしい米の香りと旨味がゆっくりと現れる。すっきりと綺麗。しかし、最後に満足感を感じる。おそらく日本酒が嫌いという人にも、愛されるのではないだろうか。
4合瓶は限定300本で、9月15日、銀座らん月のサイトで販売される。

環境も技術のうち。宮泉銘醸の美しき酒蔵
『暁霞』が生まれた宮泉銘醸の酒蔵を見せてもらった。
鶴ヶ城の城前にある立派な蔵。左の棟は大正元年につくられ、そこに70年前に継ぎ足して右の棟ができた。白い暖簾がそよぐ姿は、この蔵の威厳と清潔感を象徴しているようだ。
頑丈な分厚い壁に守られた酒は、写楽と宮泉の二つのブランド。10月からの9ヶ月間で製造を続ける。
「僕たちが造るすべての酒は、環境から造りまで一切手を抜かずに醸造しています」(宮森専務)
宮森専務が胸を張る通り、17人のスタッフがきびきびと働く。
7~9月のメンテナンス期間も、毎日機器を分解して洗い、掃除を欠かさない。
こんなに清潔で、しかもデザインとしても美しい酒蔵はなかなかないのではないか。
「菌の世界ですから。漆喰、木。すぐにカビが生えるものばかりですから。絶対に清潔な状態にしなくてはいけないんです。環境も技術のうちですから」(宮森専務)
醸造していない間も、酒母室にはリンゴやバナナの香りがほのかに漂う。
「麹室」は、杉の木づくり。
「麹室において湿度を調整してくれるのが杉の木です。杉板の呼吸作用が乾湿差の調節と結露防止を行ってくれるのです」(宮森専務)
とにかく徹底してすべての工程で、原料に関わる温度管理や環境づくりを行い、美しい飲み口、日本酒の伝統を踏まえつつ洗練された新しさをもつ酒をつくるということ。
そしてそれをつくる、蔵のあり方がここにある。
宮森社長のインタビューも、併せてぜひ読んでいただきたい。
https://frag-lab.com/special_interview/164_01.html



キャンペーンは終了しました。沢山のご応募ありがとうございました。
●「暁霞」特設サイト
https://www.nipponkodo.co.jp/akigasumi/
●純米吟醸酒「暁霞」
銀座らん月公式オンラインショップ
https://rangetsu.shop-pro.jp/?pid=187872337
●高級お香 「羅國暁霞」
日本香堂公式オンラインショップ
https://www.nipponkodo.co.jp/shop/products/detail/38985
photo by 延秀隆
https://www.instagram.com/kurubushi88/
Text by Aya Mori